| |

|
| |
 主な研究開発成果(1970〜1979年) 主な研究開発成果(1970〜1979年)
|
|
 技術情報検索手法とシステム開発に関する研究(1979) 技術情報検索手法とシステム開発に関する研究(1979) |
 研究所内には5万冊の図書、300種類の雑誌、作成された論文
研究所内には5万冊の図書、300種類の雑誌、作成された論文
報告書、収集された資料、パンフレット、写真など膨大な情
報が存在しているが、それらを一元的に検索する手段がなく
多くの研究員の悩みの種であった。まだ、コンピュータの性
能も計算速度、記憶容量の面で十分ではなく、すぐには実現
が難しく、こうした大量の情報の中から高速に応報を抽出す
るための検索手法をソフト的な観点から、データベースを用
いた高速検索手法の研究とそのシステムを開発するためのプ
ログラミング方法などの調査研究を実施した。こうした研究
は将来のデータベースシステムを用いた様々なシステム開発
へとつながって行くことになった。
|
|
 コンピュータを利用した設計計画手法に関する研究(1979) コンピュータを利用した設計計画手法に関する研究(1979) |
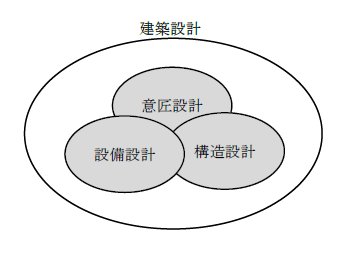 英国のホワイトヘッド博士の論文に触れヒントを得て、建築
英国のホワイトヘッド博士の論文に触れヒントを得て、建築
の設計計画の分野に応用できないかと新しい研究を始めるこ
ととした。彼は既存の病院で人の部屋から部屋への動きから
動線の距離を調査し、その総計距離から部屋同士の関係性を
接続行列とする方法を提案した。この接続行列から関係性が
強いつまり数値の大きい部屋同士は近くに配置すれば動線の
総距離が減らせ人は歩く距離を少なくできる。その点に着目
し、与えられた接続行列を基に各部屋の配置を自動的に作成
できないかというアイデアを思いつき、与えられた接続行列
や部屋の規模などの設計条件から平面型をコンピュータで計
算し平面型を図形の形で出力するシステムの開発研究に着手
した。その結果、後に「自動平面配置計画システム」として
発表することができた。
|
|
 高知学園・東京女子大学計画プロジェクト(1979) 高知学園・東京女子大学計画プロジェクト(1979) |
 本社の設計部からキャンパス計画の依頼があり、参加するこ
本社の設計部からキャンパス計画の依頼があり、参加するこ
ととなった。プロジェクトは設計に入る前の学校側の要求や
現状の課題などをまとめる作業で、具体的には現地へ行って
実態を調査し、学校側の要望などをヒアリングした。さらに
この調査結果を基に建設するキャンパスのゾーニングや必要
な施設とその規模などを計画し、大まかな概要設計案を作成
し、調査報告書として提出した。現状の調査結果から将来の
キャンパスを描き出すにはアイデアが必要で、アイデアを出
すためのブレーンストーミングやKJ法などの社会科学的アプ
ローチが有効でその方法をトライした。しかし、後で分かっ
たことだが、アイデアはそこに参加するメンバーの知識に依
存してしまい、乏しい知識をぶつけても新しいアイデアは生
まれないということであった。同じ専門分野のメンバーだけ
ではなく、多くの異なった分野の専門家と議論することが重
要だと知ることができた。
|
|
 万代シティ整備計画プロジェクト(1979) 万代シティ整備計画プロジェクト(1979) |
 新潟駅前に広大な土地を所有している新潟交通から土地を有
新潟駅前に広大な土地を所有している新潟交通から土地を有
効活用するために市民のニーズに基づいた拠点計画の策定を
依頼された。整備計画は来街者調査の結果を基にショッピン
グセンターを中心にホテル、ボーリング場などの複数の施設
を2階部分のデッキでつないで施設間を行き来できる配置を
提案した。また、全体の中央には要望のあった市のランドマ
ークとしてのタワーを建設し、観光客の誘致にも貢献する計
画となった。また、ショッピングセンターいは多くの市民が
訪れることを想定し大規模な駐車場も整備された。その結果
周辺道路の混雑が予想され、それを防止するための交通計画
には独自に開発した交通流シミュレーションシステムを用い
て、その対応策を示した。整備計画書は好評で、計画は実現
することになった。
|
|
 街路交通流シミュレーションシステムの開発(1978) 街路交通流シミュレーションシステムの開発(1978) |
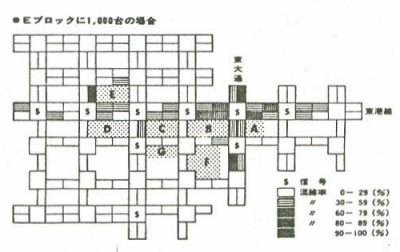 万代シティ整備計画プロジェクトにおいてショッピングセン
万代シティ整備計画プロジェクトにおいてショッピングセン
ター、ホテル、ボーリング場などの複数の建物の大規模計画
が進められる中、来店者の車で周辺の道路が混雑して問題を
起こすのではないかと言う話が持ち上がった。そうした周辺
道路の混雑具合が分かるシステムを作ってほしいという依頼
があり、交通流シミュレーションシステムを作成して対応す
ることにした。システムは、道路を数メートルのブロックの
連結で表現して、そのブロックに入る車の最大数から混雑度
を表すことにし、交通流はブロック間の車の移動で考えるこ
ととした。交通流のモデルには追従理論と言うのがあり、一
般に車は前方の車の速度に依存するという理論であった。速
度の値を用いて前のブロックに入る台数を計算して交通流と
し、ブロックで連結されたネットワークに実際に計測された
単位当たりの車を入れ、それを単位時間毎に計算して、ブロ
ック内の車の台数から混雑度を表示させた。このシステムは
駐車場の配置計画にも使われ評判となった。
|
|
 万代シティ来街者調査プロジェクト(1977) 万代シティ来街者調査プロジェクト(1977) |
 N市駅前に大規模な商業施設の拠点開発の計画の話が持ち上
N市駅前に大規模な商業施設の拠点開発の計画の話が持ち上
がり、一般の市民から希望する施設などのニーズを聞くため
の来街者調査を始めることとなった。来街者調査はアンケー
トに答えてもらうため、歩いている市民に、直接声をかけて
調査する方法をとった。事前に質問票を作成し、回答を調査
者が記録するため数日をかけて数百枚の回答を得た。回答を
得るためにはコミュニケーション能力が求められ、調査の目
的や開発企業などを伝え、ティッシュを上げるなど手を尽く
した。こうした調査には信頼感を持ってもらうことの大切さ
が必要だと痛感した。回答から得られた施設の他に公園や緑
地などを希望する市民が多かった。しかし、実際に公園へ行
ってみると誰もいなくて、使われてもいない様子で、実態と
ニーズの乖離があることが分かり調査方法を見直すいいきっ
かけにもなった。
|
|
 物的流通施設の適正配置に関する研究(1976) 物的流通施設の適正配置に関する研究(1976) |
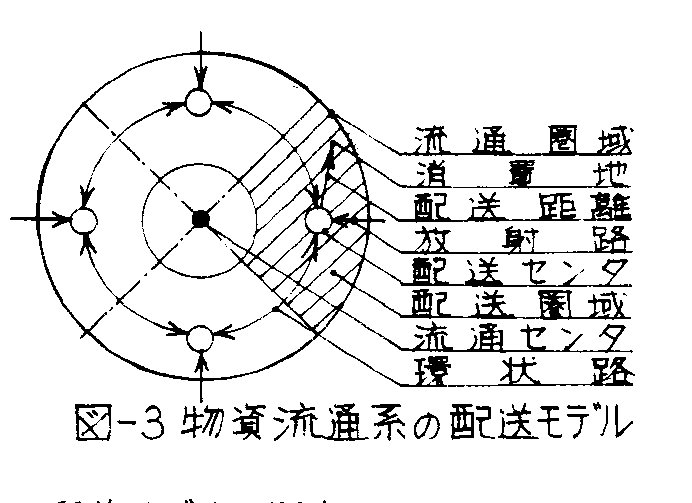 物的流通施設の都心集中化はトラック輸送の増加を伴い都市
物的流通施設の都心集中化はトラック輸送の増加を伴い都市
部の交通混雑を招く要因となっていて、この問題を解決する
ため流通施設の適正配置に関する研究に着手した。物資流通
系の配送モデルを集中化モデルと分散化モデルに分けて、配
送の数学的モデルを提示して、配送距離の積分による数値計
算によって、その最小化の配置パターンを求めるものであっ
た。いくつかの配置パターンを計算した結果、流通施設を圏
域によって分散化し、その最適化を図ることができることを
示した。距離最小をコスト最小に置き換えれば様々な立地分
析にも応用可能であり、また、距離指標が重要な避難施設の
配置や施設の利用計画などにも適用可能な方法であった。
|
|
 ハフの確率モデル・グラフ理論を用いた地域施設配置手法の研究(1976) ハフの確率モデル・グラフ理論を用いた地域施設配置手法の研究(1976) |
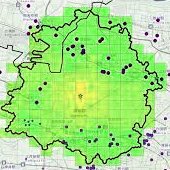 グラフ理論を研究している中で、本社の都市開発部で施設配
グラフ理論を研究している中で、本社の都市開発部で施設配
置に関するニーズがあることが分かり、勉強会を始めた。配
置手法を調べていてハフの確率モデルに出会った。この理論
は施設の規模が大きい程人を引き付ける力があり、逆に施設
との距離が遠い程その力が弱くなるというものであった。こ
のモデルとグラフ理論を組み合わせて、地域施設を適正に配
置するための手法の研究に取り組むこととした。ハフの手法
は地域の人口とその人口の今後の伸びを考慮する方法が流行
り始め、各社が同じ方法で計算するため出店場所が同じにな
ってしまい津田沼に同時に大規模な施設が出現し「津田沼戦
争」などとと呼ばれ新聞記事にもなった。
|
|
 グラフ理論を用いた施設の適正配置(1975) グラフ理論を用いた施設の適正配置(1975) |
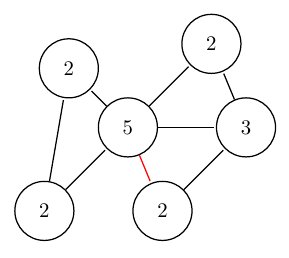 グラフ理論はノード(点)の集合とエッジ(線)の集合で構成さ
グラフ理論はノード(点)の集合とエッジ(線)の集合で構成さ
れるグラフに関する数学の理論で、たとえば、鉄道や路線バ
ス等の路線図は、駅(点)がどのように路線(線)で結ばれてい
るかをグラフで描くことができる。このつながり方に着目し
て、地域の人口ポテンシャルや施設の規模ポテンシャルなど
を点に、線を地域間の距離や時間距離などに置き換えて施設
の適正配置に応用できないかと考えた。当時、最先端だった
この数学理論を使って試行錯誤の結果、一つの点から全ての
点に行く最短距離の総和を各点毎に計算できるので、点のポ
テンシャルを変えた時の変化を計算すれば適正な配置を決定
できるのではないかと思ったが、膨大な計算量になって、ス
マートな方法ではなかった。
|
|
 空間の計量と評価に関する研究(1975) 空間の計量と評価に関する研究(1975) |
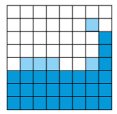 設備制御システムは商品化され、そのための専門部署ができ
設備制御システムは商品化され、そのための専門部署ができ
本格的に販売がなされることとなった。研究所から本社への
技術移転も進み、研究所で生まれた技術が商品化された最初
の技術成果として高い評価が得られた。そこで、以前から暖
めていた空間の計量と評価に関する新たな研究に着手するこ
ととし、全く異なった分野への方向転換を図った。今まで、
あまり着目されてこなかったグローバルなスケールでのアプ
ローチで、建築を捉えることを考えた。それは、以前のよう
に単体の建築を研究対象にするのではなく自然の中の建築群
として捉えるものであった。自然環境そのもの、あるいは建
物群の用途や規模などを対象にその計量化を図り、当時、流
行っていたメッシュ法を用いて、メッシュ毎に分割された対
象空間を数値化し、そのポテンシャルを評価するといった方
法に着目した研究であった。
|
|
 インテル8080用クロスアセンブラーの開発(1974) インテル8080用クロスアセンブラーの開発(1974) |
 富士通のU200上に開発した設備制御システムであったが、今
富士通のU200上に開発した設備制御システムであったが、今
までのシステムは全ての処理を中央のコンピュータ 1台で処
理していて、中央に負荷がかかり過ぎる問題があり、プロセ
ス側に当時最先端を誇っていたインテル8080のマイクロコン
ピュータを導入し負荷分散を図ることとした。そこで、U200
のコンピュータ上のアセンブラー言語で書いたマイクロコン
ピュータのプログラムを作成するためのクロスアセンブラー
を開発した。その結果効率よくマイクロコンピュータのプロ
グラム作成ができ、今後の分散システムの基礎を築くことが
できた。
|
|
 U-200リアルタイムモニターシステムの改良開発(1974) U-200リアルタイムモニターシステムの改良開発(1974) |
 開発した設備制御システムは BECSS(ベックス)という商品名
開発した設備制御システムは BECSS(ベックス)という商品名
でデビューすることが決まり、そのために富士通のU200とい
う新たなコンピュータを導入することとなった。しかし、そ
のリアルタイムOSはローリン・ロールアウト機能を多用し
ているため処理速度が遅く、使い物にならなかった。そこで
以前、開発した設備制御のためのリアルタイムOSのノウハ
ウを生かして、高速にマルチ処理をするシステムに改良開発
した。これらの基本的なアルゴリズムは、現在においても
プログラム開発には欠かせない機能となっている。
|
|
 設備制御システムの開発の全貌を論文発表(1974) 設備制御システムの開発の全貌を論文発表(1974) |
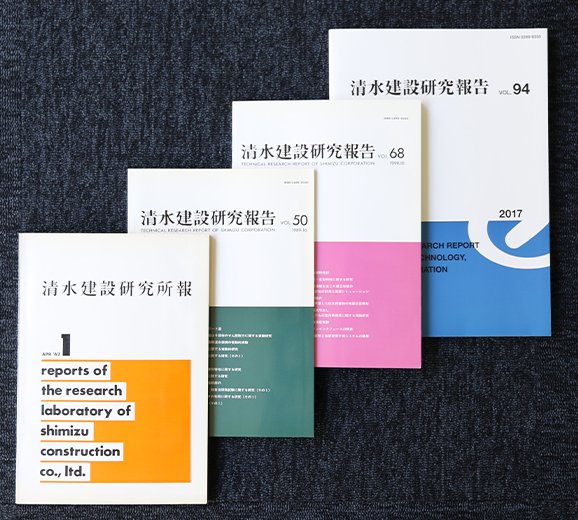 日本で初めてのコンピュータによる建築設備の自動制御シス
日本で初めてのコンピュータによる建築設備の自動制御シス
テムであり、空調、電気、衛生、防災の各設備機器を統合的
に制御し、設備の自動運転を可能としたビルディング・オー
トメーションの開発の全てを業界に知らせることとした。そ
の全貌を研究所報・空調学会・建築学会などへ論文投稿し研
究発表を行った。コンピュータによる無人運転という触れ込
みで多くの専門家の関心を集めた。他に建築、設備等の雑誌
などからの執筆の依頼も多くあり、当社の技術レベルの高さ
を一般に知らせる広報活動にも貢献した。
|
|
 対戦用立体4目並べプログラム(1973) 対戦用立体4目並べプログラム(1973) |
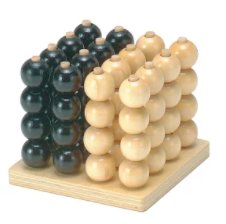 当時では画期的なゲームプログラムであったが、オセロに継
当時では画期的なゲームプログラムであったが、オセロに継
ぐ 2匹目のドジョウで人気はイマイチだった。もう一つの問
題はグラフィックディスプレイ上に、この立体をどのように
表現するかといった表示方法だった。裏側や中央は見えなく
なってしまうので 4層に分けて表示したり、いくつか試みた
が、みんなからは不評で人気はでなかった。これもコンピュ
ータが手を読んで人間と対戦するように作った、どこにもな
い傑作であったが、すぐに飽きられて終わってしまった。
|
|
 設備制御用言語処理インタープリターの開発(1973) 設備制御用言語処理インタープリターの開発(1973) |
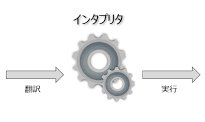 プロセスとの入出力を中心とした設備制御プログラムはアセ
プロセスとの入出力を中心とした設備制御プログラムはアセ
ンブラーという機械語とほとんど変わらない言語で記述して
いたが、作成効率が悪く、それを具体的な設備等の名称で記
述できる言語を設計し、それを処理する言語処理インタープ
リターを開発した。具体的には冷水バルブの流水量を 3段階
にや部屋番号X1の温度は、などと記述することでコンピュー
タの言語に詳しくない技術者でもプロセスの制御システムを
作成することができた。インタープリターは解釈実行という
意味で記述された文を 1行づつ読取りながら実行して行く方
式で、今ではHTMLなどの処理に利用されている。
|
|
 日本初の設備制御システムの開発・本格稼働(1972) 日本初の設備制御システムの開発・本格稼働(1972) |
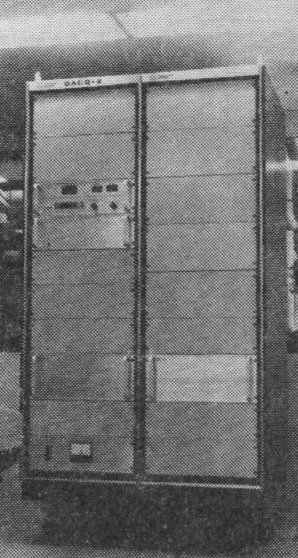 独自に開発した DOSと1kアセンブラーを使って本格的な空調
独自に開発した DOSと1kアセンブラーを使って本格的な空調
・電気・衛生・防災の建築設備全般をコンピュータによって
制御するシステムの開発に着手した。一例を上げれば、例え
ば部屋の温度を取込んで、その部屋の最適温度と比較し、暑
ければその階にある空調機の冷却バルブを開ける操作信号を
出して部屋の温度を適切に保つといった制御を行う。こうし
た室内温湿度制御をはじめ動力機器のスケジュール発停、熱
源管理、ポンプの台数制御、監視ロギングなどを、電気設備
においてはデマンド管理、力率制御、電力量管理、故障管理
機器運転管理など、殆ど全ての設備の自動化を目指した。ま
た、そのために具体的な設備名を使って入出力を行う制御用
のマクロ言語を開発し、プログラム開発の効率化を図った。
システムは1972/12本格稼働した。
|
|
 ミニコン用サブルーチン・ライブラリー等の開発(1972) ミニコン用サブルーチン・ライブラリー等の開発(1972) |
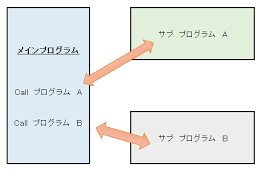 メーカーから提供されたソフトには技術計算用のサブルーチ
メーカーから提供されたソフトには技術計算用のサブルーチ
ンやアプリケーションプログラムを効率よく開発するための
ユーティリティ・プログラムがあった。ただ、実際に使って
みると、浮動小数点演算、三角関数などの初等関数などのラ
イブラリーに多くのバグが見つかり、ミニコン用のサブルー
チン・ライブラリーやユーティリティ・プログラムの全てを
新たに開発することを余儀なくされた。面倒な作業であった
が、この経験で、たとえば三角関数はアークタンジェントか
ら作成し、これを基にコサインを、サインはその逆関数なの
で簡単に作ることができた。これらの初等関数のほとんどは
多項式近似を使って作られていることも分かり、いい勉強を
させてもらった。
|
|
 リアルタイムDOSおよび1kアセンブラーの開発(1972) リアルタイムDOSおよび1kアセンブラーの開発(1972) |
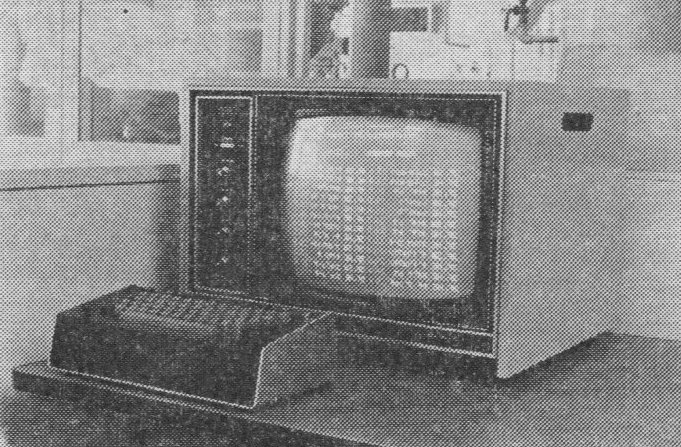 設備制御用のアプリケーションプログラムが増えていく中で
設備制御用のアプリケーションプログラムが増えていく中で
メモリーは増設できないため当時新しく開発された磁気ドラ
ムを導入してプログラムの増えるのに対応することとした。
そこでリアルタイムOSをディスク・オペレーティング・シス
テムに改善して増加するプログラムをドラムに内蔵して起動
要請があるたびに呼び出してスタートさせる機能をOSに持た
せた。今では当たり前の DOSを世界に先駆けて開発した。ま
た、同時にプログラム言語であったアセンブラーを1kワード
に圧縮して、ドラムとのロールイン・ロールアウト方式でメ
モリーを殆ど使わないシステムにした。もちろん、リアルタ
イムシステムなので設備の運用管理制御中に同時に開発がで
き、 1台のコンピュータで行うことを可能にした。マイクロ
ソフト社が数年後にシングルタスクの DOSを発売したのだが
こちらはマルチタスクの DOSを作っていたので、これを商品
化しておけば億万長者になれたと今でも言われている。
|
|
 対戦用オセロプログラム(1972) 対戦用オセロプログラム(1972) |
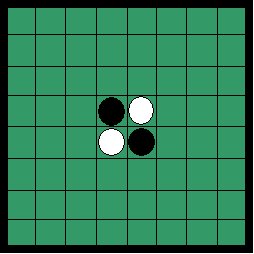 世界初の対戦用のゲームプログラムで、当時の最新鋭のグラ
世界初の対戦用のゲームプログラムで、当時の最新鋭のグラ
フィックディスプレイを用いて、すばやく数手先の手を読む
本格的なシステムであった。オセロは駒が反転してしまうた
人間にとっては数手先を読むのも難しく、このプログラムは
2〜3手先を読むだけで、人間に勝つことができた。それに指
し手の数も少なく、当時の遅いコンピュータには向いていた
昼休みにはみんなが列をなして対戦していたが負け知らずの
強い存在だった。このプログラムは、もちろん設備制御中の
コンピュータで実際の仕事と同時に遊ぶことができ評判は良
かった。オセロプログラムは、現在の将棋、マージャンなど
のゲームソフトのさきがけとなった。
|
|
 新研究所に設備制御システム導入(1972) 新研究所に設備制御システム導入(1972) |
 新研究所の開設を前に設備やコンピュータの試運転を行う時
新研究所の開設を前に設備やコンピュータの試運転を行う時
期 (1972/09頃)から新家屋に入り設備制御システムの開発に
取組んだ。コンピュータと実際の設備をつなぐ作業は設備業
者も初めてで何もできず、MDF の配線表の作成から実際の配
線作業もこちらでやる羽目になった。400 チャネルのクロス
バー交換機、FACOM-RのデジタルインターフェイスとMDFの配
線、さらに MDFと実際の設備との配線は1000点を越える膨大
な量で何日もかかる作業だった。建物は地上 6階、建築面積
は 127万平米、熱源方式は熱回収型エアソースヒートポンプ
方式、空調はファンコイルユニット併用各階ユニット方式、
熱源は蓄熱層を使った蓄熱式を採用した。実際の設備と MDF
を介して接続されたコンピュータによって一点一点毎の接続
テストを繰返し、動作やセンサーの正常性の確認などに追わ
れた。また、停電時にコンピュータと非常電灯が作動できる
ように蓄電池を備え、バッテリーが無くなるとディーゼル発
電機を自動でスタートさせた。さらに、コンピュータ側には
CVCF(安定化電源)からの電源供給を行い電圧と周波数の安定
化を図った。
|
|
 FACOM-Rリアルタイムモニターおよびユーティリティシステムの開発(1971) FACOM-Rリアルタイムモニターおよびユーティリティシステムの開発(1971) |
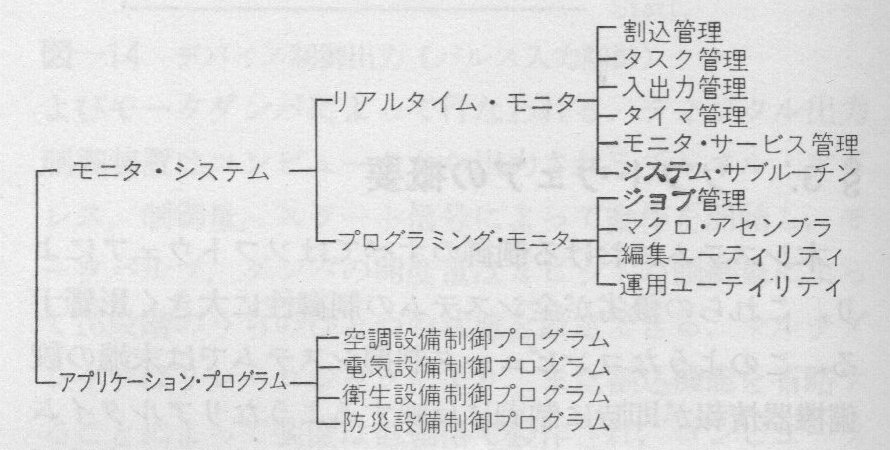 同時に動作する建築設備を 1台のコンピュータであたかも同
同時に動作する建築設備を 1台のコンピュータであたかも同
時に動かすためには、それらを制御するためのリアルタイム
システムが必要であった。今のリアルタイムOSのことを当時
はリアルタイムモニターと呼んでいた。設備等の動作はコン
ピュータから見れば緩慢で遅いので、従来のバッチ処理だと
設備が動作している間は、コンピュータは処理が終わるまで
待つことになる。そのため、起動信号を送った後は周辺の装
置とは切り離す必要ある。周辺装置は自身の処理が終了した
段階でコンピュータに終了の信号を送る。この信号を受取っ
てコンピュータは処理の終了を知る。この知らせる機能を割
込みと言い、この機能がハードウエアとして内蔵されて初め
てリアルタイム処理が可能となる。今回は16本のプログラム
を同時に動作できるように設計した。モニターから見たプロ
グラムの単位はタスクと呼ばれ、そのタスクを制御すること
をタスク処理と言う。また、通常の運転中に火災警報などの
緊急信号を受取って、その処理をすぐにやるためにタスクに
動作の順番を持たせて行う優先処理の機能などもシステム化
した。モニターシステムはリアルタイム処理に必要なこうし
た割込み管理、タスク管理、入出力管理、タイマー管理を行
う。また、コンピュータの操作作業を補助し、アプリケーシ
ョンプログラムの作成、デバッグなどをサポートするユーテ
ィリティプログラムを作成した。
|
|
 建築設備の自動制御に関する研究(1970) 建築設備の自動制御に関する研究(1970) |
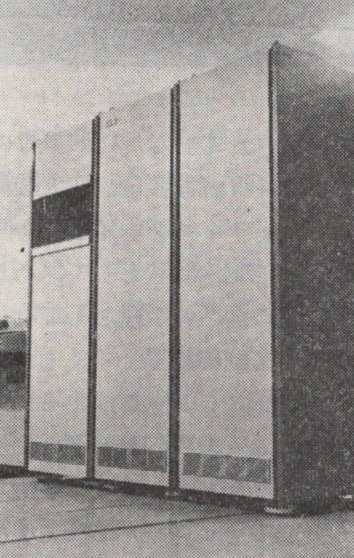 建築設備をコンピュータで自動制御しようとする日本で初め
建築設備をコンピュータで自動制御しようとする日本で初め
ての研究をスタートさせた。この試みは米国が最初であった
が空調機だけの単純なもので、本研究の対象とした設備は、
空調・電気・衛生・防災の全てに及び、これらの無人化運転
を目指した。設備からの情報は 400チャネルのクロスバー交
換機を通して、また、設備への制御信号は MDFを介して送ら
れ、リアルタイムに動作させることができた。建築の設備は
動作が同時に起こることは日常の現象で、例えば空調制御中
に火災警報器が鳴るなどは普通のことである。ところが、当
初導入した富士通のモニターシステムはバッチ処理で、こう
した同時に起こる処理に対応できていないことからリアルタ
イムモニターの開発に着手した。さらに、制御用のマクロ言
語などの開発も行い、各室や熱源などの温度情報の入手やバ
ルブの開閉などの制御情報をプロセスに送出できた。コンピ
ュータ内には、こうした制御用の AD-DA変換器やデジタル入
出力のインターフェイスを備え、開発したリアルタイムモニ
ターのタスク処理によって16の機器を同時に制御可能とした
プログラムからバルブの動作信号を出して、空調機械室へ走
って行き、動作が確認できた時の感動は今でも忘れられない
本研究の全体は研究所報Vol.22(1974.4)掲載されている。
|
|



|