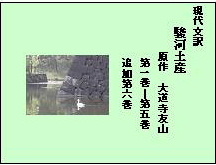写真は旧江戸城和田倉門付近
話題の90%以上は1600年の関が原の戦い以後、徳川家康の天下となりますが、その時から大坂夏の陣で豊臣家が滅亡、翌年家康が他界するまで、その間16、7年の家康の逸話を集めています。 特に1605年の隠居後大御所として駿府から江戸幕府をコントロールする様子が生々と書かれており、家康は政治家として非常に合理主義者である事もよく表現されています。
解読の底本には国立公文書館内閣文庫の駿河土産(159-054)を使い、参考として同文庫別写本(159-053)を参照しています。(20070211)